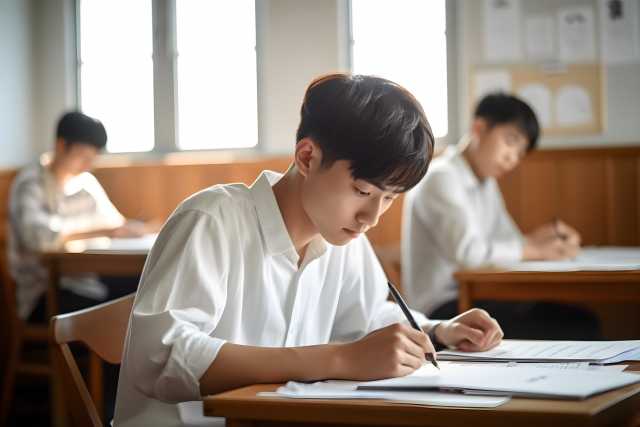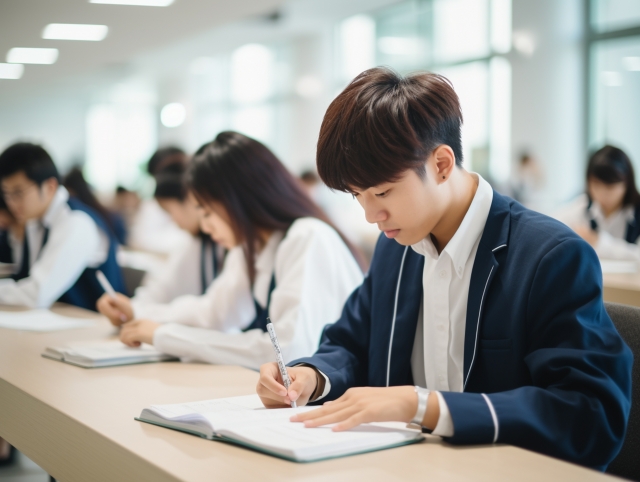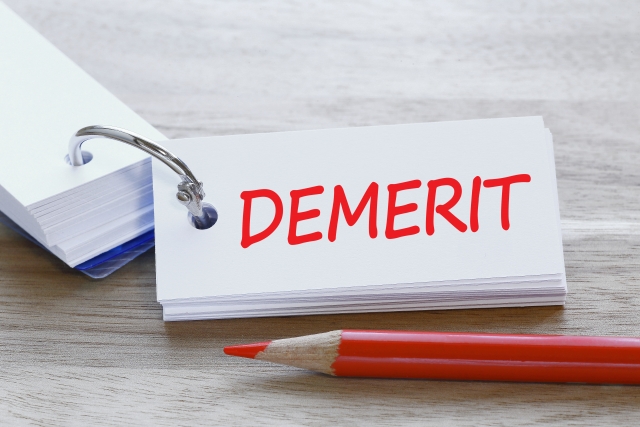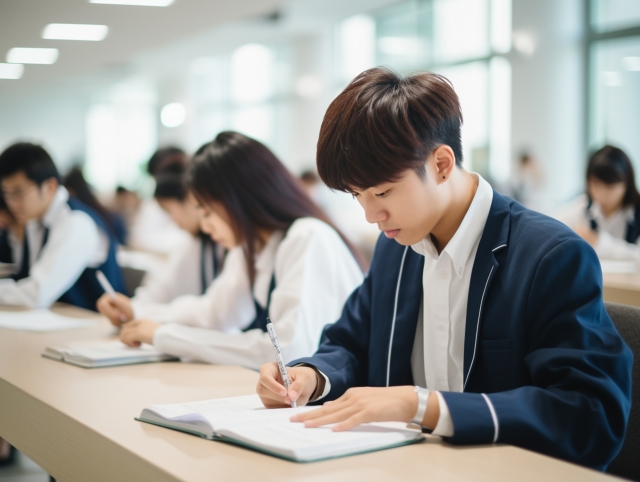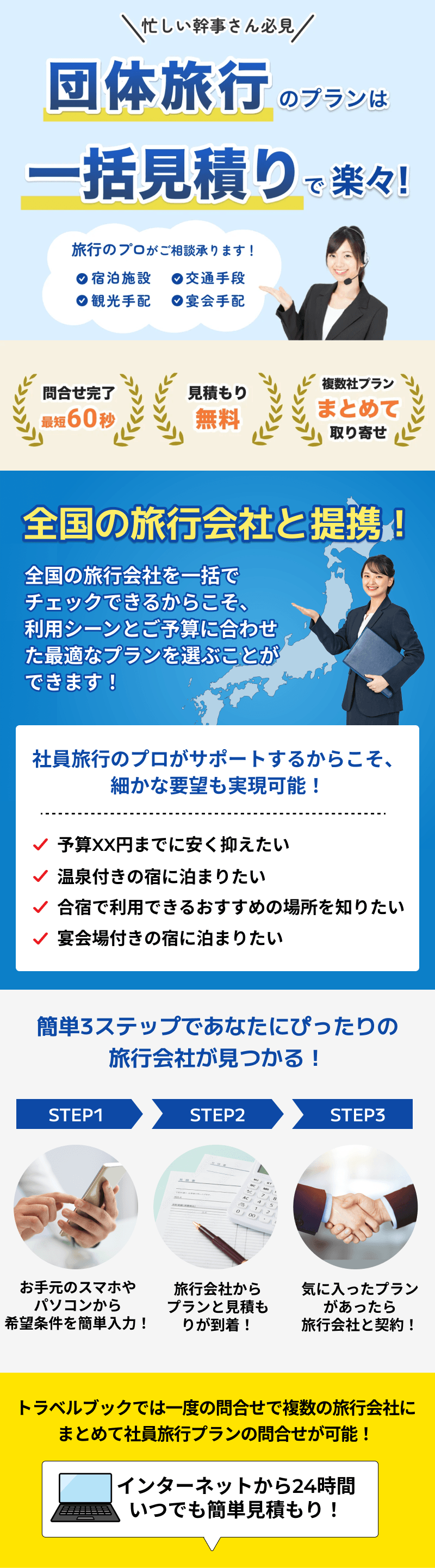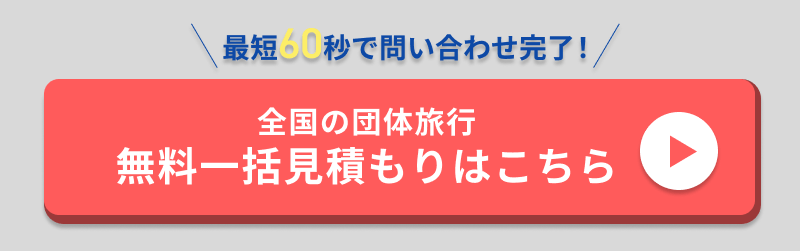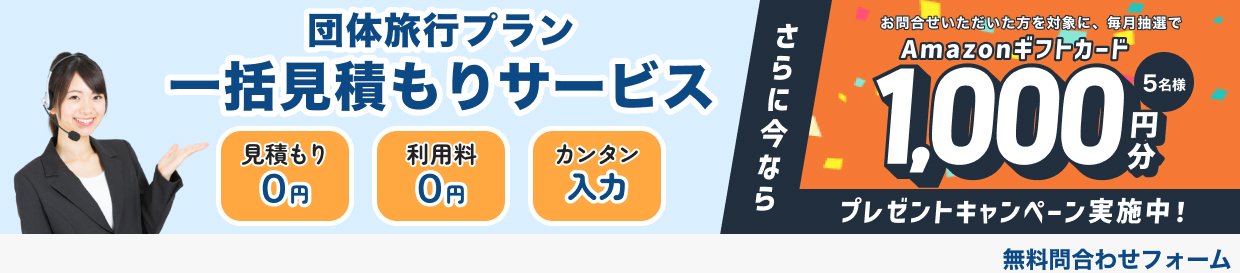勉強合宿の行き先はどう決める?かかる費用は?合宿のメリット・デメリットも紹介!
勉強合宿はどうやって決める?何に注意すればいい?そもそも勉強合宿って何をするの?
この記事では、勉強合宿のメリット・デメリットを踏まえながら、行き先の決め方やおすすめの場所まで勉強合宿に関する様々な情報を紹介します。
勉強合宿とは?
「勉強合宿」とは、春休みや冬休み、春休みといった長期休暇を利用してホテルや研修施設に泊まり込んで勉強をする合宿です。「参加者が集中して学習できる環境」を作ることが最大の目的であり、食事や睡眠、休憩を除く1日の大半を勉強に費やすことになります。
合宿期間は2~3日の短期合宿から、数週間にわたる長期合宿まで様々。塾や予備校が実施するもの、学校(小中学校、高校、大学)で実施するもの、社会人向けに開催されるものなど、実施する団体により期間も内容も違ってきます。
塾や予備校の勉強合宿
大手の塾や予備校では、学力向上や成績アップのために勉強合宿を行うケースが多く見られます。長期休暇中に開催されることが多く、学校主催の勉強合宿と比べると期間が長め(特に長いと1~2週間程度)という特徴があります。
小中学校の勉強合宿
私立の小学校や中学校では勉強合宿が行われることもあります。目的は苦手科目の克服や、中学受験・高校受験対策などが挙げられます。
高校の勉強合宿
高校になると公立校でも勉強合宿を行う学校が増えてきます。大学受験に向けての勉強の他、苦手科目の克服や日々の勉強で生まれた疑問解消という目的もあります。
大学の勉強合宿
大学の勉強合宿はゼミが主催する「ゼミ合宿」であるケースが多いです。なお、理系のゼミの場合は「研究室の合宿」という呼ばれ方が一般的。ゼミや研究室以外にも、サークルや有志で行われる勉強合宿もあります。
社会人
社会人が参加できる勉強合宿もあります。「趣味の知識を深めるため」「資格取得のための勉強を集中して行いたい」「研究者としての見識を深めるため」など勉強合宿に参加する理由は様々です。
最近ではIT関係の勉強合宿が盛んに行われています。プログラミング合宿やチームビルディングを目的とする合宿、集中してソフトウェアの開発を行う合宿など内容も多彩です。
いずれの勉強合宿も、非日常の空間で行うことで効率よく勉強できるというメリットがあります。
勉強合宿のメリット
勉強合宿について、「家でも勉強できるのにわざわざ合宿に行くのは面倒くさい」「行くための時間がもったいない」そんな風に考えている方もいるかもしれません。しかし、勉強合宿はわざわざ行くに値する数々のメリットがあるのです。
長時間勉強できる集中力が身に付く
勉強合宿では勉強に集中できる環境が整えられています。さらに食事やお風呂、睡眠、休憩時間を除いて1日の大半を勉強して過ごす、まさに勉強中心のスケジュールです。受験に向けた学習塾の勉強合宿の場合、1日に10時間以上も勉強するケースも。慣れないうちは長時間の勉強を辛く感じるかもしれませんが、合宿が終わるころには長時間の勉強に耐えられる集中力を身に付けることができるはずです。家で一人で勉強しているだけでは、そこまでの集中力を付けるのは難しいもの。一旦、集中できるようになれば、その後の受験勉強にも役立ちます。
また、合宿中に「自分がどうやったら集中力を持続させられるのか」について模索してみるのも良いでしょう。集中力を高めるためのルーティンやリフレッシュ法などを考えてみるのも良いかもしれませんね。
ライバルから刺激を受けられる
勉強する目的や苦手分野、得意科目などは人それぞれなので、勉強は自分自身との戦いだとも言えます。しかし、仲間のいない環境で自分一人で勉強しているだけではモチベーションが下がってしまうこともあるでしょう。「本気で勉強に打ち込む仲間やライバル」がいる勉強合宿への参加は、必ずモチベーションアップへとつながるはずです。
正しい生活リズムの中で勉強できる
受験生の夏休みともなると部活も引退してしまい、生活リズムが乱れてしまう子もいると思います。ゲームなどで夜更かししてしまうことで朝早く起きれず、昼近くにようやく起床、というような生活になってしまうことも。生活リズムが乱れると勉強に対するやる気も起きず、勉強に集中できないまま夜を迎えてしまう、なんてことにもなりかねません。
しかし、起床や就寝、食事時間などがスケジュール化された勉強合宿に参加すれば、自然と正しい生活リズムが身に付きます。一旦、規則正しい生活リズムを身に付けることができれば、勉強合宿終了後も役に立つでしょう。
分からない箇所や疑問をすぐに質問できる
子どもが勉強を継続できない理由の一つに「分からない箇所や疑問をすぐに解決できない」という点が挙げられます。勉強中に分からないところがあると、「調べるのが面倒くさい」「分からないからもうやめよう」というように、モチベーションの低下につながってしまうことも。しかし、勉強合宿に参加すれば身近に講師がいてくれるため、分からない箇所もその場ですぐに質問できます。疑問をすぐに解決できるので学習効率が上がり、モチベーションアップにも効果的です。
勉強合宿のデメリット
メリットの多い勉強合宿ですが、人によってはデメリットに感じられる部分もあります。
ストレスを感じてしまう
勉強合宿では講師や仲間と一緒に勉強をするため、常に周りに人がいます。人の目があるからこそ勉強に集中できるというメリットがある反面、人によってはストレスに感じてしまうこともあります。静かな環境で勉強したい人にとっては、小さな話し声やペンを走らせる音なども、集中力を欠く原因になりかねません。また、勉強中だけではなく休憩中や就寝時も一人になれる時間が確保しにくいこともストレスの一因と言えるでしょう。
とはいえ、実際の試験は周りに人がいる環境で実施されます。ペンの音などの適度な雑音には慣れておくために、あえて参加するという選択肢もあります。
燃え尽き症候群になる可能性がある
勉強合宿終了後は達成感があり、「翌日1日くらいは勉強しなくてもいいや」と思ってしまう人もいるでしょう。勉強を休むのが翌日だけであればよいのですが、そのままズルズルと勉強に身が入らなくなってしまう「燃え尽き症候群」になる可能性も否定できません。勉強合宿に参加したことで満足してしまうのではなく、その後も計画的に勉強を進めていきましょう。
自分のペースで勉強できない
勉強合宿では起床や食事、就寝時間などもスケジュール化されています。また、塾によっては時間割ごとに勉強する科目や内容まで決まっていることもあります。「とりあえず勉強に集中したい」「何から手を付けたらよいか分からない」というような場合は勉強合宿に参加して強制的に勉強漬けの日々を過ごすことはメリットになりますが、すでに勉強習慣が身に付いているのであればデメリットになりかねません。
例えば「早起きして勉強したい」「夜の方が集中できる」「苦手な科目や単元に力を入れたい」というような場合、スケジュールや時間割が細かく決まっている勉強合宿への参加はあまりメリットが感じられないこともあるでしょう。
勉強効率が下がってしまう
学習塾の勉強合宿では、クラスごとに決まった同じ課題や問題に取り組む、というケースも少なくありません。与えられた課題が自分にとってレベルが高すぎる、もしくは低すぎる場合、かえって学習効率が下がってしまうこともあり得ます。また、時間割が決まっているので自分の苦手な科目や克服したい分野に勉強時間を充てることができなくなってしまいます。苦手がはっきりしている人にとっては、無駄な時間を費やすことになってしまうのでデメリットと感じられてしまうでしょう。
勉強合宿にかかる費用
勉強合宿はさまざまなメリットがある反面、開催者にとっては大きなコストがかかるというデメリットがあります。ここでは勉強合宿を開催する際に必要となる主な費用と、コストを抑えるためのポイントを紹介。初めて勉強合宿を実施しようとしている場合はチェックしておきましょう。
勉強合宿の主な費用
・宣伝費
勉強合宿を行う場合、事前に参加者を募るための宣伝を行う必要があります。学校などで実施する合宿の場合はプリントなど、学習塾や予備校の場合は、新聞の折り込みチラシや看板、広告などが一般的な宣伝方法として挙げられますが、これらの媒体を利用するとコストが高くつきがちです。
最近ではウェブサイトやSNS、動画配信などを通じて参加者を募る方法も多く見られます。これらは無料で利用できるものがほとんどなので、費用を抑えることも可能。あらかじめ塾や予備校のアカウントを作成しておき、普段から地道に宣伝活動を行っておくとより効果的です。
・宿泊・滞在費
勉強合宿で必要となる大きな費用のひとつが宿泊・滞在費です。宿泊施設の使用料や食事代、勉強を行う会場の使用料などが含まれます。これらの費用を少しでも抑えたいなら、「学習施設一体型ホテル」を選ぶのがおすすめです。これは学習用の部屋やレストランが併設されている宿泊施設のこと。学習には会議室やセミナールームなどの広間を利用できるか問い合わせてみるといいでしょう。またホテルの中にレストランなどがあれば、食事を別に手配する必要もありません。宿泊施設の中で合宿に必要なものがすべて備わっているため、わざわざ外に出る必要もなく、時間を有効に活用できます。主催者側にとっては、参加者の行動管理がしやすいというメリットも。また移動の必要がなければ、それだけ移動費などのコスト軽減にもつながるのでおすすめです。
初回は短期合宿から
学習塾や予備校などで開催される勉強合宿は、長期休暇を利用して数週間みっちり行うケースが多いようです。ただし初めて勉強合宿を実施する場合、いきなり長期間の合宿プランを立てるのは、コストの面でもリスクが高くおすすめできません。まずは2~3日程度の短期合宿を行い、実施内容や宿泊先の選び方、費用などについて様子を見るのがいいでしょう。
勉強合宿の行き先の決め方
勉強合宿を企画する際、まず悩むのがどこで実施するかです。勉強合宿は、どのような場所で開催するかによって、成果が左右される場合があります。ここでは勉強合宿の行き先を決める際、気をつけておきたいポイントを紹介。より良い環境で合宿を行い、充実した時間を過ごしましょう。
静かで落ち着いた場所
勉強合宿で必要なのは、勉強に集中できる環境です。もし勉強会場が繁華街などにあり、周辺からの騒音が聞こえてきてしまうと、思うように勉強がはかどらない場合があります。また人の出入りが多いなど、施設内も条件によっては騒がしい場合があるので注意が必要です。誰もが集中して取り組めるよう、落ち着いた立地のところや、防音性の高い部屋のところなどを選びましょう。
また周辺に緑が多い環境もおすすめです。勉強の合間に気分転換したい時、緑や自然があるとリフレッシュでき、勉強にもより集中しやすくなります。
合宿先が遠すぎずアクセスが良い
合宿先が遠いと、それだけ移動に時間がとられ、本来の目的である「勉強の時間」が削られることになります。また移動距離が長いとそれだけコストがかかってしまうデメリットも。できるだけアクセスしやすいエリアで、条件にあった場所を選ぶのがおすすめです。
宿泊場所と勉強会場が近い
勉強合宿を行う場合、勉強会場と宿泊場所をそれぞれ用意する必要があります。勉強会場と宿泊場所は、離れすぎているとそれだけ行き来するのに時間とコストがかかってしまうので、近場で探すようにしましょう。もし宿泊するホテルに大きい会議室や広間がある場合、そこを勉強会場として使用するのもおすすめ。同じ施設内で宿泊と勉強を行えれば、効率もよくスケジュール管理もしやすくなります。
必要な設備が整っている
勉強合宿はどのようなスタイルで実施するかによって、必要なものが変ってきます。あらかじめ準備するものを確認しておきましょう。自前のものを持ち込むことも可能ですが、ホワイトボードやプロジェクターなどの大きなもの、運ぶのが大変なものは、レンタルできると便利です。会場を選ぶ際は、必要なものが備わっているかどうかも注目しておきましょう。
最近では動画を使用した授業も多いので、会場のWi-Fi環境も確認しておくと安心です。
また、勉強合宿で参加者同士の親睦を深めたり、最終日に達成感を味わったりするレクリェーションを企画するケースもあります。バーベキューや食事会、キャンプファイアーなどをみんなで楽しむのがその一例。宿泊施設の中にはこれらのアクティビティに対応しているところもあるので、施設を選ぶ際は注目しておくと便利です。
ニーズに合った宿泊形態に対応している
宿泊施設を選ぶ際は、合宿の期間にもよりますが、長期利用に適した快適な部屋を選ぶようにしましょう。参加人数に応じて、シングル・ツインなどの個室タイプにするか、大部屋でまとまって宿泊するかを検討し、ニーズに合った宿泊形態に対応しているところを選択してください。よほど大人数でない限り、全員が入れるような大部屋を利用すると目が届きやすく安心です。
また勉強合宿中は、食事をどのようにとるかもポイントです。もし参加者が各自で食事をとるとなると、勉強場所から一度外出する人も出てくるでしょう。外へ出ることは気分転換になりますが、主催者にとっては行動管理がしにくくなるデメリットも。そのため食事の用意は、主催者側が行うとスケジュール管理もしやすくおすすめです。もし宿泊施設となるホテル内に勉強会場がある場合、食事付のプランを選んでおくといいでしょう。
会場利用時間に融通が利く
勉強会場を選ぶ際は、時間の融通が利く施設がいいでしょう。進行状況によっては、合宿最終日に時間を延長するケースも出てきます。この場合、施設によっては延長料金が発生してしまい、費用面の負担が大きくなることも。もしもの時に快く時間を延長できるよう、あらかじめ余裕をもって利用時間を設定しておくか、時間に融通が利く施設を選んでおくと安心です。
勉強合宿におすすめの場所
勉強合宿をする場所を選ぶ際は、アクセスの面や周辺の環境が整っているかどうかがポイントです。ここからは、勉強合宿を行うのにおすすめの場所を東日本・西日本それぞれ2ヶ所ご紹介します。
【東日本】
①長野県
首都圏からだけでなく、北陸や中京圏からもアクセスしやすい長野県。バスや車、新幹線や在来線と、さまざまな手段で訪れることが可能です。県内には避暑地として人気のある高原が複数あります。暑い夏でも気温が低いので過ごしやすく、緑に囲まれた静かな場所なので勉強合宿にぴったりです。スポーツ合宿が行われることも多い地域のため、団体での宿泊利用がしやすいのが特徴です。
②神奈川県
神奈川県は東京からのアクセスが良好で、特におすすめなのが箱根エリアです。自然豊かな土地で、勉強に集中できる環境が整っており、温泉がついている宿も多いので、1日の終わりにリフレッシュすることが可能。観光スポットも多く、長期合宿の際は気分転換のアクティビティが取り入れやすい場所です。
【西日本】
①奈良県
奈良県は大阪や京都などから行きやすく、豊かな自然に恵まれたエリアが多い土地。全館貸切可能な団体宿泊施設もあるので、合宿しやすい環境が整っています。県内には日本を代表する歴史的建造物が多いので、気分転換も兼ねて歴史を学びに訪れるのもおすすめです。
②兵庫県
交通の便が良く、さまざまなエリアがある兵庫県。通年型のリゾート地として知られている神鍋高原は、暑い夏でも気温が低く、合宿利用を歓迎している宿が多くあるので、勉強合宿に適しています。また、観光スポットとして人気の高い淡路島もおすすめ。合宿を専門にしている温泉付きのホテルや合宿向けプランを用意している宿が多く、神戸や大阪からのアクセスも良好です。
以上、計4ヶ所エリアをご紹介しましたが、この他にも勉強合宿の実施が可能なエリアはいろいろあります。旅行代理店への相談も行いながら、自分たちの予算や移動時間などの希望に合った勉強合宿先を見つけましょう。
勉強合宿Q&A
勉強合宿でよくある質問を3つご紹介します。
Q.勉強合宿を行う理由は?
A.合宿を行うことでスマホやゲームなどから必然的に離れる時間が増え、勉強に集中しやすい環境が整えられます。また、合宿中は長時間勉強することになるため、長時間の勉強や試験に耐えられる力を身につけることが可能。そして、仲間とともに勉強することで、勉強に対するモチベーションをアップさせられます。さらに、疑問点が生じた時もすぐ教員へ質問できるなど、メリットが多いので勉強合宿が行われています。
Q.1日に何時間くらい勉強する?
A.勉強合宿では、食事や睡眠時間以外は基本的に勉強を行うため、1日の勉強時間は約11〜16時間になります。
Q.補助や手当はある?
A.自治体によっては合宿を行う団体に対して、補助金などを出しているところもあります。合宿を行う前に申請が必要な自治体もあるので、合宿を計画している段階で補助金等についても確認を行いましょう。旅行代理店に相談するのもおすすめです。